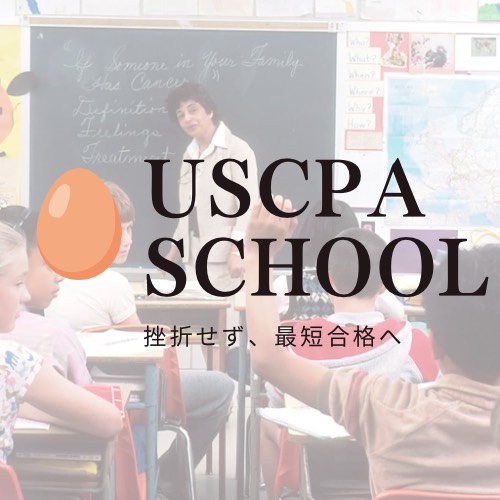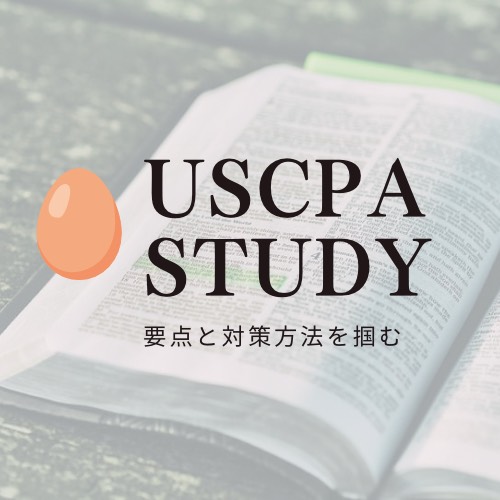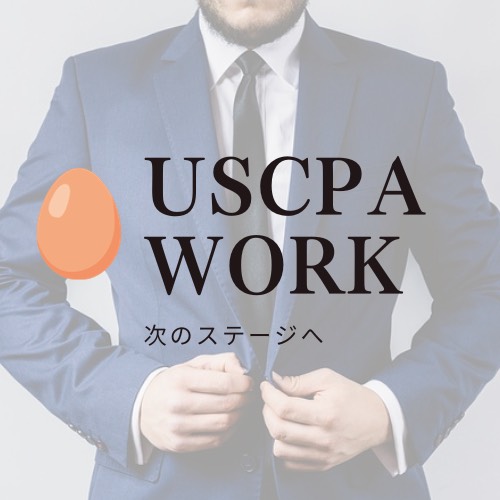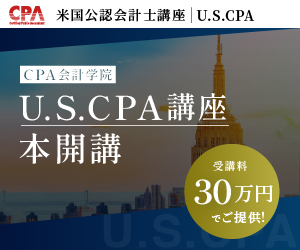USCPAを勉強している方・勉強しようとしている方、
絶対AIを活用してください。
約束ですよ
USCPAの特徴として、とてつもなく難解な内容はありませんが、範囲は膨大なので、学習を始めてみたものの、テキストの分量に圧倒され「時間が足りない」「効率よく進められない」と多くの受験生が途中でペースを崩してしまいます。
ですが、最近では従来のテキストや講義に加え、動画教材やAIを組み合わせることで、疑問を即解消し、非常に効率的に勉強できる環境になっています。
この記事では「なぜ今、生成AIを使うべきなのか」、そして「具体的にどう使えばUSCPA学習を加速できるのか」を、実践的な方法とともに解説します。
合格への近道を探している方にとって、必ず役立つ内容になるはずです。
自分に合った予備校を見つける
今なら無料パンフレット有
USCPA学習に生成AIを活用すべき理由
- 動画教材の登場で学習効率は飛躍的に向上
- USCPAは確立された分野なのでAIの回答精度が高い
- 学習範囲は変わらないが効率が大きく変わる
USCPA試験の学習は、広大な範囲の理解が求められるため、多くの受験生が「時間が足りない」と感じています。受験生は社会人が多いですし、効率的に学習を進めていく必要があります。
動画教材の進化が効率学習を後押し
そもそもなんですが、生成AIの前に動画教材があるっていうのが大きいです。動画教材によって「繰り返し視聴できる」「再生速度を自由に変えられる」という学習環境が整っています。
例えば、苦手な範囲だけをピンポイントで見直すことも、全体を1.25倍速で一気に復習することも可能です。これにより「講義をもう一度聞きたい」「理解が浅い部分だけ強化したい」というニーズに柔軟に対応でき、効率的な学習が実現しました。
ここに生成AIを組み合わせると、動画を見て理解した内容を即座にAIに質問して確認できます。単なる「受け身の学習」から「双方向で深める学習」へと進化するのです。



今20代前半の人には当たり前かもやけど、
わしからしたら基本的にテキストでの学習が中心やった。
確立された分野だからこそAI回答の精度が高い
生成AIを勉強に活用する上で不安に思うのは、「正しい答えが返ってくるのか?」という点かもしれません。しかし、USCPA試験で扱う会計基準や監査手続きは、基本的にすでに確立された分野です。



これめっちゃ大きくて、
最新の事例や個別具体の事例は不適やけど、
USCPAのような内容はめっちゃ適してるで
そのため、AIが返す答えの再現性や安定性は非常に高く、安心して学習に取り入れることができます。「なぜこの処理が正しいのか」「監査手続きの順序はどうなるのか」といった疑問に対して、AIは根拠を含めて答えてくれます。
つまり、生成AIは“迷ったときの即答パートナー”として機能し、理解を深めながら次に進むスピードを落とさないのです。
注意点
注意すべきは 生成AIの回答を盲信しないこと です。AIはときに表現を簡略化したり、試験の文脈とは異なる解釈をすることもあります。
最終的な判断基準は、あくまで公式テキスト・基準書・予備校教材です。AIは「理解を深める補助ツール」であって、答えそのものを保証する存在ではありません。
したがって、AIの解説で納得したとしても、必ずテキストに立ち返って確認することで、安全かつ確実な学習につながります。
勉強範囲は変わらないが効率は劇的に変わる
USCPAの学習に必要な知識量や深さは、生成AIを使っても変わりません。覚えるべき基準は膨大で、理解すべき監査の流れも複雑です。
ただし、生成AIを使うかどうかで「効率」はまったく別物になります。従来ならテキストを何度も読み返したり、講師に質問して返答を待ったりしていた時間を、AIなら即時に解決できます。
この違いは、最終的に「どれだけ復習できるか」「どれだけ応用練習に時間を割けるか」という形で表れます。同じ範囲を学習しても、効率の差が合否に直結する――それが今のUSCPA学習における現実です。
「勉強しないのは損」と言える時代に必要な一歩
- 学習効率を高める技術が誰でも使える時代
- 生成AIを使うか否かで大きな差が生まれる
- 一歩踏み出すかどうかが合否やキャリアを左右する
USCPAの学習は膨大な知識を短期間で吸収する必要があり、効率の差がそのまま合否につながります。これまで「時間が足りない」「復習が追いつかない」と悩んできた受験生にとって、生成AIは時間を味方につけるための強力なツールです。



つい3,4年前に断念した人も、
今改めて再チャレンジを考えてもいいレベルでゲームチェンジしてる。
勉強のハードルが劇的に下がったこの時代に、あえて勉強しないことは“最大のリスク”になります。
動画教材や生成AIで「いつでも・どこでも・誰でも」効率よく学べる環境が整った今、学ばない選択は単に努力しないことではなく、チャンスを手放すことを意味します。
さらに、現代は動画教材やAIといったテクノロジーを活用すれば、従来の勉強法よりも圧倒的に効率的に進められます。にもかかわらず、従来のやり方に固執してしまえば、他の受験生に置いていかれるリスクが高まります。
たとえば、疑問点をそのままにせずAIに即質問して解決できる人と、テキストを何度も読み返して時間を浪費する人。
同じ範囲を学んでいても、積み重ねれば数十時間単位の差となり、最終的に合格可能性を左右します。
生成AIを活用する方法①:問題を写真に撮ってアップする
- 問題を写真で撮影→AIにアップすれば即解説
- 正解だけでなく“なぜ間違いか”まで理解できる
- 時間短縮と理解の深まりを同時に実現
USCPAの勉強で最も厄介なのは「分からない問題に出会ったときに、立ち止まってしまうこと」です。テキストを読み返しても解決しなかったり、答えだけを覚えてしまったりすると、学習効率は大幅に下がります。
そこで有効なのが、問題を写真に撮って生成AIにアップする方法です。
たった数秒で疑問を解消できるだけでなく、理解の精度を格段に高めることができます。
写真でアップするだけで疑問を即時解決
従来、問題の解説を確認するには参考書や講義テキストを探し直したり、予備校に質問して返答を待ったりする必要がありました。これでは1つの疑問を解消するのに10分以上かかることも珍しくありません。
一方で、生成AIに問題文の写真をアップすれば、その場で解説が返ってきます。正解の選択肢はもちろん、他の選択肢がなぜ誤っているのか、どの論点に関わるのかまで即座に提示されるのです。
たとえば監査の問題で「どの証拠がより信頼性が高いか」を問われたとします。AIに写真を送れば、単に「Aが正解」ではなく、“外部の独立した資料は内部資料より信頼性が高い”といった原則を踏まえた理由まで説明してくれます。
時間短縮と理解の深まりを両立できる
USCPA試験の学習範囲は膨大で、すべてを網羅するには効率が欠かせません。その点、写真アップによるAI活用は、疑問解消にかかる時間を劇的に短縮してくれます。
1問につまずく時間が1分に収まれば、1日あたりの学習進度は大きく変わります。さらに、AIが示す「誤答理由」や「関連知識」の解説によって、単なる暗記ではなく本質的な理解につながります。
この積み重ねが、復習の手間を減らし、結果として学習全体の効率を底上げするのです。つまり、“写真を撮ってアップする”というシンプルな行為が、合格への近道になると言えるでしょう。
実例を使って解説
AICPAサンプルテスト:https://www.aicpa-cima.com/resources/article/get-familiar-with-the-cpa-exam-by-practicing-with-our-sample-tests
実際にAIを活用して問題を解いていきたいんですが、例えば、サンプルテストの監査報告書の「再発行(reissue)」に関する問題です。
もし、何を問われている問題なのか、答をどう選べば良いのか全然わからない、という場合はまずはざっくり質問するだけで良いです。問題文を写真でアップロードすると、AIは以下のように、何を問われているか、選択肢ごとの正誤と理由を整理して返してくれます。
- わかりやすく解説して
-
この問題は 監査報告書の「再発行(reissue)」時にCPAが取るべき手続きに関する論点です。ポイントを整理して解説します。
■問題文の要旨
以前の監査クライアントから「過去の監査報告書を再発行してほしい」と依頼された。
CPA は再発行前に何をすべきか?
■選択肢の検討
・Obtain a letter of representation from the former client’s management.
→ ✅ 正解。
理由:監査報告書を再発行する場合、CPAは「報告書日以降に財務諸表に影響する事象が発生していないか」を確認する必要があります。そのために、前クライアントの経営者から再度「経営者確認書(management representation letter)」を入手することが求められます。
・Make inquiries of the former client’s attorney regarding pending litigation.
→ ❌ 必要ありません。訴訟に関する確認は通常の監査手続きですが、再発行の際に必ず弁護士に問い合わせを行う必要はないです。
・Review the former client’s records to verify its compliance with debt and loan agreements.
→ ❌ これは新しい監査のような手続きであって、「再発行」には不要です。
・Consider whether there is substantial doubt about the former client’s ability to continue as a going concern.
→ ❌ Going concern の検討は監査当時にすでに行っていることなので、再発行の際に改めて実施する必要はありません。
※AIの回答そのまま載せているので、内容の確からしさはテキスト等を参照お願いします。
注意点
本記事では「問題を写真に撮って生成AIにアップする」という活用法を紹介していますが、これはあくまで 個人の学習目的 に限定した利用を想定しています。
著作権のある教材を丸ごとスキャンして配布したり、内容をそのまま公開することは、著作権侵害につながるリスクがあります。
生成AIを活用する方法②:自身の理解・疑問を言語化してアップする
- 理解を言語化することで学習の定着度が高まる
- AIに文章で投げると誤解や不足を指摘してもらえる
- 予備校の短いやり取りをAIで補完できる
USCPAの学習では「知識を覚える」だけでは不十分です。本当に理解できているかどうかは、自分の言葉で説明できるかどうかで決まります。
そこで効果的なのが、自身の理解や疑問を文章化してAIにアップする方法です。単なる暗記では到達できない、応用力を伴った学習につながります。



こちらから発信することで双方向で学習を深められることが大きい。
学校の授業と違ってUSCPAの勉強はどうしても受動的になりがち。
言語化することで理解が深まる仕組み
人は「理解したつもり」でも、いざ説明しようとすると言葉に詰まることがあります。これは、知識が断片的に頭の中にあるだけで、論理的に整理できていない証拠です。
そこでAIを相手に、自分の理解を文章で説明してみましょう。例えば「収益認識の5ステップはこういう流れで…」と書き出して送れば、AIは論理の飛躍や不足している要素を指摘してくれます。
つまり、自分の説明を“模擬面接”のように添削してもらえるのです。これにより「知っている」から「説明できる」へと理解が一段階進化します。
疑問や誤解をAIに補正してもらう
予備校や教材で疑問を質問できる場面は限られています。一方でAIなら、疑問点をそのまま文章化して投げかければ、即座に解説を返してくれるのが大きな強みです。
例えば「監査証拠の入手手続きと評価の違いが曖昧」と書けば、AIは定義の違いや関連する事例まで整理して説明します。また、自分の説明に誤りがあれば、その根拠を示しながら修正してくれるので、誤解が早い段階で正されます。
このように、短時間で質の高い“疑問解消サイクル”を回せることが、AIを使う最大のメリットです。学習効率を上げるだけでなく、理解の精度を大幅に高められます。
実例を使って解説
AICPAサンプルテスト:https://www.aicpa-cima.com/resources/article/get-familiar-with-the-cpa-exam-by-practicing-with-our-sample-tests
さっきの問題なんですが、解説(AIの解説)を見ても、時に「まだモヤモヤが残る」ケースがあります。
たとえばなぜ選択肢③が「再発行するなら、念のため再確認した方が安全では?」と疑問が浮かんだ場合は「なぜ正解なのか?」「なぜ不正解なのか?」と自分の言葉で整理してAIに投げかけます。実際に質問すれば、AIは背景まで補足して深堀りしてくれます。
つまり、ただ解説を受け取るだけでなく、自分の疑問を表に出すことで理解の深さが一段階進むのです。これこそが「AIに疑問を言語化してアップする」最大の価値だと言えるでしょう。
- Review the former client’s records to verify its compliance with debt and loan agreements. → ❌ これは新しい監査のような手続きであって、「再発行」には不要です。
この選択肢③の解説に関して、
→再発行するんだからreview等した方がよくない?
→review以外の手続きは必要?
→前年度の意見内容によっては必要? -
「再発行するのだから、もう一度レビュー(確認)した方が安全では?」という感覚は自然です。ですが、監査基準上は 「再発行」=新しい監査をやり直すことではない というのがポイントなんです。
■「再発行」と「再監査」の違い
- 再発行(reissue):過去の監査報告書を、依頼に応じて再度提出する行為。意見は「当時の監査基準日までの財務諸表」に対して有効。
- → 再監査ではないので、新しい監査手続き(契約遵守の検証など)は不要。
- 再監査(reaudit):過去の財務諸表について再度監査を実施し、新しい意見を表明する場合。
- → こちらは当然「compliance の確認」や「弁護士照会」など、新しい監査手続きが必要。
■再発行時にCPAが行うべきこと
必須手続き:
- 前クライアント経営者からrepresentation letterを再取得する
(報告書日以降に重大な変更がないか、経営者に責任を持って確認させる) - 必要に応じて、その後のイベントを調べるための限定的な質問を行うことはある(例:重要な訴訟が起きていないか、後発事象がないかなど)。
不要な手続き:
- 借入契約遵守の確認(選択肢③)
- going concern の再評価
- 弁護士への再照会
これらは 新しい監査をやる場合に必要なもの。再発行では範囲外。
■イメージでまとめると
- 新しい監査:財務諸表をもう一度フルで調べる(訴訟、契約、ゴーイングコンサーンなど全部)。
- 再発行:過去の監査報告書をもう一度渡すだけ。その前に「その後重要な変化がないですよね?」と経営者に確認するだけ。
- 再発行(reissue):過去の監査報告書を、依頼に応じて再度提出する行為。意見は「当時の監査基準日までの財務諸表」に対して有効。
※AIの回答そのまま載せているので、内容の確からしさはテキスト等を参照お願いします。
生成AIを活用する方法③:基準やフローを整理・図解させる
- 複雑な基準やフローは文字だけで理解しづらい
- 生成AIなら要点整理や図解化が一瞬で可能
- 視覚的に理解することで記憶定着が高まる
USCPAの学習では、会計基準や監査の流れなど、体系的な理解が求められる分野が数多く登場します。しかし、テキストだけで学ぶと情報が断片的になり、全体像を把握しにくいのが実情です。
そこで役立つのが、生成AIに基準やフローを整理・図解させる方法です。複雑な概念を「見える化」することで、効率的かつ深い理解につながります。
文字情報をAIに整理させて全体像をつかむ
例えば収益認識の「5ステップ」や、監査計画から報告までのプロセス。これらをテキストで追うだけでは、全体のつながりや位置づけをイメージするのが難しいことがあります。
そんなとき、AIに「収益認識の5ステップを表で整理して」と指示すれば、一目で流れが分かる一覧を返してくれます。監査の流れも「計画 → 実施 → 評価 → 報告」といったプロセスを時系列で整理し、要点をまとめてくれます。
こうして全体像を先に押さえることで、細部の理解がスムーズになり、学習効率が大幅に向上します。
図解による「見える化」で記憶定着を高める
さらに有効なのが、生成AIに図解を依頼することです。内部統制のフローや財務諸表監査の証拠収集プロセスなどは、図にすることで直感的に理解できます。
「内部統制の流れをフローチャートで図解して」と指示すれば、テキストでは見えなかった因果関係や役割分担が一目で把握可能です。また、複雑な会計基準もマインドマップ風に整理すれば、知識同士のつながりが可視化され、記憶の定着度が格段に高まります。
文字だけに頼らず、AIを「学習の図解パートナー」として使うことで、理解の質とスピードを両立できるのです。
↓実際にCOSOの内部統制フレームワーク(組織の内部統制を設計・運用・評価するための基本モデル)の5つの構成要素をまとめてもらった表です。
| 要素 | 概要 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 統制環境 (Control Environment) | 内部統制の土台。経営者の姿勢や倫理観、組織文化を含む。 | – 経営者の誠実性と倫理観- ガバナンス体制- 権限と責任の明確化- 人材の能力確保 |
| リスク評価 (Risk Assessment) | 目的達成に影響を与えるリスクを識別・分析し、対応を決定する。 | – 目的の設定- リスクの識別と評価- 不正リスクの考慮- 変化への対応 |
| 統制活動 (Control Activities) | リスクに対応するために設ける方針や手続き。 | – 承認・承認プロセス- 職務分掌- 資産の保全手続き- IT統制 |
| 情報と伝達 (Information & Communication) | 必要な情報を適時に取得し、関係者に伝達する仕組み。 | – 内部情報の流れ- 外部とのコミュニケーション- 報告ラインの明確化 |
| モニタリング活動 (Monitoring Activities) | 内部統制が有効に機能しているかを継続的に評価。 | – 継続的モニタリング- 内部監査- 不備の是正とフォローアップ |
※AIの回答そのまま載せているので、内容の確からしさはテキスト等を参照お願いします。



個人的には教科書に情報を全部集約させるタイプやけど、
いろんな観点で違いを表にまとめてもらうとめっちゃわかりやすい。
生成AIを活用する方法④:実務シナリオや英語要約に使う
- 試験知識を実務シナリオに落とし込むと応用力が育つ
- 英語要約で国際的な表現力を同時に磨ける
- 合格後を見据えたキャリア活用につながる
USCPAの学習は試験に合格することが最終ゴールではありません。むしろ合格後には、実際の会計・監査・財務の現場で知識をどう使うかが問われます。
そのために効果的なのが、生成AIを実務シナリオや英語要約に活用する方法です。試験対策とキャリア形成を同時に進めることができます。



これは結構使ってない人多いのでは?
教科書的のボリューム的に具体例が少ない時とかに、
具体例をもらうとわかりやすくなる。
実務シナリオで学習内容を“仕事の形”にする
USCPAの試験範囲は、実務と直結するテーマが多く含まれています。しかし、ただ暗記するだけでは「現場でどう使うのか」が見えてきません。
そこでAIに「海外子会社の監査を想定したシナリオを作成して」と依頼すれば、実務で起こり得る流れをシミュレーションできます。契約締結から証拠収集、リスク評価に至るまで、実務的なプロセスを具体例として学習に組み込めるのです。
さらに「監査報告でよくある質問を想定して」と指示すれば、試験問題を超えた応用練習にもなります。このようにAIを活用することで、合格後に役立つ実務感覚を学習中から鍛えることが可能です。
英語要約で国際的な表現力を磨く
USCPAは国際資格である以上、英語力も避けて通れません。特に専門知識を英語で説明する力は、試験後のキャリアで大きな差になります。
生成AIを使えば、学習した内容を「英語で要約して」と依頼するだけで、適切な専門用語や表現が得られます。例えば「収益認識の5ステップを英語で200語にまとめて」と指示すれば、実務でそのまま使える英語表現のストックが作れます。
また、自分が書いた英文をAIに添削してもらえば、自然で正確な表現に磨き上げられます。こうして学習と同時に英語力を高めることは、国際的な場面で通用する会計プロフェッショナルへの近道となります。
まとめ
USCPAの学習は、実際に1年〜2年の長期戦となるくらい範囲が広いですが、生成AIを取り入れることで学習効率を劇的に高め、合格への道筋を明確にできる時代になりました。
動画教材による効率化はすでに当たり前になりつつあり、さらにAIを活用すれば「疑問解消」「言語化トレーニング」「基準の図解」「実務シナリオや英語要約」といった形で、学習の質を飛躍的に引き上げることが可能です。
大切なのは、いきなり完璧に使いこなすことではなく、小さく取り入れて試してみる一歩です。その積み重ねが、試験合格だけでなく、キャリア全体で価値を発揮できる力につながっていくはずです。



何度も言うけど、
勉強のハードルがめっちゃ下がったこの時代に勉強しないリスクはめっちゃ大きいで
自分に合った予備校を見つける
今なら無料パンフレット有